(『バイヤーズ・ガイド』編集発行人 永瀬正彦)
今回は展示会のブース作りや試食の準備、来場者への声がけについてお話しします。展示会も商談会もズバリ準備がすべてです。本番では練習以上のことは起こりません。
ブース作りを展示会設営時に行っていませんか?
事前に社内で納得のいくブースを作っておこう!
展示会に出展する時、皆さんは“いつ・どこで”ブース作り(商品展示・演出等)を行っていますか? おそらく展示会前日の設営時にブース作りを行っていませんか?
というのも、設営時になって初めてブース作りをしていると、商品展示で試行錯誤したり、機材の調子が悪かったり、備品を忘れて慌てて買いに行ったりすることになり、あっという間に退出の蛍の光が流れます。
仕方なく翌日に持ち越して展示会初日に続きの作業をしていると、開場の時間となり、バイヤーが来場してバタバタで始まってしまった経験はありませんか?
こうしたことがないように、私は展示会の1週間前に社内で納得のいくブースを作ることをおすすめしています。
納得のいくブースを作ったら、スマートフォンでブースを撮影し、使用する備品をすべて段ボールに詰めて会場に送ります。会場に着いたらスマートフォンの画像を確認しながら、納得のいくブースを再現すれば良いのです。こうすれば1〜2時間程度で納得のいくブースをつくることができます。
ブース作りで重要な “コンセプト” と “差別化”
ブース作りのポイントは、やはりコンセプト(出展の目的・展示商品の優先順位)を決めることが重要です。その上で、造作・テーブルクロス・ポスター・のぼり・POP・衣装・キャラクターなどフル活用して、他のブースとの差別化を図るのです。

平台に平置きだと来場者の視界に入りませんので雛段で立体的に演出する、展示台の両端を高くして中央を低くすると中をのぞいてみたくなる“お城・洞窟の法則”を活用するのも手です。来場者の催事に出店した時のイベントスペース、販売ブースのイメージで、売り場を意識した展示も良いアピールに繋がります。
また新型コロナウイルスの影響もあり、シールドやマスク、除菌スプレーなど衛生管理への意識はますます重視されます。
コロナ禍の今、試食用の商品サンプル開発に取り組もう!
バイヤーをブースに惹き付けるための試食の用意も重要です。“どうしたら上手く商品を伝えられるか?一番美味しく試食してもらうには?”を念頭に置いて、試食方法・ポーション(大きさ)・他商品との食べ比べなど、商品の味わいを演出しましょう。
ただし最近の新型コロナウイルスの感染リスクを考慮すると、会場での実演による試食ではなく、私は試食用の商品サンプル配付をおすすめしています。新型コロナウイルスの感染リスクから、小売店での催事販売でも試食は難しくなっています。
こうした観点からも、試食用の商品サンプル配付は有効だと思いますので、今から開発に取り組んでみると良いでしょう。
出展目的で来場者への呼びかけ方は変わる!
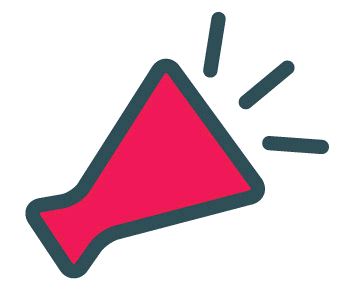
展示会で自分のブースに引き込むためには、来場者への声がけが重要となります。
皆さんは会場でどのような声がけを行っていますか?
|
【声がけの例】 A:どうぞご覧ください B:ご試食いかがですか? C:○○県の××市から来た、◎◎の美味しいお米です。 D:楽天で大賞を取ったアイス、限定100 食のご試食です。 E:○○県のかまぼこの食べ比べにご協力ください。アンケートにお答えいただくと粗品を差し上げています。 |
上記例のAやBと答える方が多いかと思いますが、実は誰もが言える内容なので、自社ブースに行く動機につながりません。
そこでAやBの最初にCを加えることで、呼びかけに自己紹介をセットにすることができます。
またDであれば、優秀な商品であることに加え、限定試食による人集め効果が期待できます。
最後のEであれば、アタックリストの入手と粗品という名のサンプル提供を行っています。このように目的に合わせた呼びかけ方法があるのです。
名刺やサンプルを来場者に“いらない”と言われたら

最後に皆さんが展示会会場で名刺や資料・サンプルを渡そうとして、来場者にいらないと言われたらショックですか?
|
A:かなりショック!! B:特になんとも思わない。 C: むしろうれしい!! |
初出展の方はAという方も多いかも知れませんが、皆さんの名刺や資料・サンプルを求めていない来場者の名刺は必要でしょうか?
というのも、もしも皆さんに興味を持っていない人の名刺を受け取ってしまったら、展示会終了後にフォローアップをしないとならないのです。
展示会の会場で成約見込みの◎△×のクリーニングを行った方が効率的なので、皆さんの名刺や資料がいらないということは“不要な名刺をもらわなくて良かった!”とポジティブに捉えて、どんどん前に進んで行きましょう。
シリーズ『商談成功の秘訣!』のその他のコラムはこちら
当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。
公開日
